
JR東日本高崎支社は2024年6月6日、主に蒸気機関車の補機として運用されているEF64形2機・EF65形1機・DD51形2機の旅客運用終了を公表しました。
近況とともに、今後なんらかの活用があるのか、解体されるのかも考えます。
着々と進んだ機関車代替

JR東日本ではこれまで、ブルートレイン廃止後の機関車牽引列車として残されていたレール輸送・バラスト(砕石)輸送の工事用列車の気動車化が進められており、2017年にはレール輸送用のキヤE195系の量産先行車、2021年にはバラスト輸送と車両牽引用を兼ねたGV-E197系の量産先行車が登場(過去記事)しています。
その後はそれぞれ数年間の試験ののち量産が実施され、2021年3月改正からレール輸送用のキヤE195系が(過去記事)、2024年4月ごろからバラスト輸送用のGV-E197系が運用を開始しています。
このほか車両牽引用として、GV-E197系の電車版となるE493系電車も2021年に量産先行車・2023年に量産車が登場。2024年5月にはキハE130系1両と当初設計に比べると最小構成ながら車両牽引を開始(過去記事)しています。
そして2024年5月には、GV-E197系が12系を牽引する試運転が実施されていました。今回はこの試運転の結果を受けて公表に至ったものと推測できます。
JR東日本が以前掲げていた、2024年度の機関車牽引列車の淘汰はある程度は順調に進行していることが分かります。
発表を見る
今回の公表(JR東日本 PDF)では、『「電気機関車(EL)」と「ディーゼル機関車(DL)」について、車両の老朽化に伴い、2024 年の秋をもって旅客列車としての営業運転を終了』とされています。
運用終了車両は、JR東日本ぐんま車両センター(旧:高崎車両センター高崎支所)所属のEF64形の1001号機と1053号機、EF65形の501号機、DD51形の842号機と895号機の5両の電気・ディーゼル機関車です。
先述の通り既に事業用途についても置き換えが進んでおり、ほぼほぼこれらの機関車は引退イベントを以って運用機会を失うものとみて差し支えない状態です。
ファイナル運転として、9月15日から10往復20本の列車をDL・ELの牽引で設定することが示され、このうち夏の臨時列車分が公表されました。
| 列車名 | 始発駅 | 終着駅 | 編成 |
| DLぐんま10fin | 高崎9:47 | 横川10:49 | DL+12系4両+EL |
| ELぐんま10fin | 横川14:15 | 高崎15:18 | EL+12系4両+DL |
| ELぐんま9fin | 高崎9:47 | 桐生11:55 | EL+12系4両+DL |
| DLぐんま9fin | 桐生14:07 | 高崎16:04 | DL+12系4両+EL |
| DLぐんま8fin | 高崎9:47 | 横川10:49 | DL+12系5両+EL |
| ELぐんま8fin | 横川14:15 | 高崎15:18 | EL+12系5両+DL |
| ELぐんま7fin | 高崎9:56 | 水上12:03 | EL+12系5両+DL |
| DLぐんま7fin | 水上15:15 | 高崎17:14 | DL+12系5両+EL |
使用機関車は未定とされています。運転方面と組成が毎回微妙に異なる設定で、列車名もカウントダウンと凝っている印象を受けます。
決まり次第お知らせする内容として「ヘッドマークのデザイン」と触れられており、なんらかのヘッドマークが掲げられそうです。
なお、鉄道コム取材(外部リンク)によると、今後のSL運行で補機が必要な場合はGV-E197系を使用するとしています。
公表された各形式の近況
EF64形

山岳用電気機関車であるEF64形のうち、1000番台は1980年より53機が投入された国鉄最後の直流電気機関車となっており、JR東日本には1001号機・1029〜1032号機・1051〜1053号機の8機が継承されています。
このうち高崎運転所〜高崎車両センター高崎支所〜ぐんま車両センターと高崎一筋だった1001号機は、お座敷列車「くつろぎ」や旧型客車などの牽引を目的にぶどう色に白帯のスタイルで長らくイベント列車で運用されてきました。
2017年に全般検査が施工された際に国鉄色かつ各部の窓のゴム色が登場時の白色に復元されて引き続き人気の機関車となっていました。
その他のJR東日本に継承された7機は長岡運転所〜長岡運転区〜長岡車両センターに配置され、上越線方面の寝台特急牽引に使用されてきました。1029号機が若くして度重なる故障から除籍されたほか、1030〜1032号機には電車牽引用の双頭連結器が装備されています。
寝台特急全廃後は配置先が別れ、1030〜1032号機と1051号機は長岡に残留した一方で、1052号機と1053号機は高崎車両センター高崎支所に転属。EF64形0番台に代わり、中央線エリアのレール輸送などを中心に使用され、1052号機は2021年に一足先に引退となっています(過去記事)。

今後の動向については不明瞭ですが、1001号機にはトップナンバーとして保存車としての価値が認められるかもしれません。1053号機も国鉄最後の直流電気機関車のラストナンバーといった意味こそありますが、どちらかを保存するとなれば1001号機が選ばれそうです。
JR東日本では先述の通り、両機のほかにも新潟車両センター所属の1030〜1032号機と1051号機の4機が残存しています。
1030〜1032号機は2023年に全般検査が施工されて電車牽引用・上越線と信越線の霜取り列車としての活用が残りそうですが、工事列車の仕事が無くなった1051号機の今後が心配されます。
1051号機と1053号機は外部組織が手を挙げれば幸運な未来があるかもしれません。
新潟にゆかりがある鉄道車両の保存実績に長けた新津鉄道資料館さん、鳥塚社長退役後にどの程度の熱量があるかが未知数な直江津D51レールパークさん、入手に動いてくれることに期待したいところです。
JR貨物では中央西線・伯備線用として多数のEF64形1000番台が運用されていますが、こちらもEH200形進出(過去記事)により少しずつ数を減らしています。
EF65形の置き換えが急速に進行しましたので、こちらもいざ本格的に後継機投入が開始されれば一気に数を減らしそうです。
EF65形

EF65形のうち500番台は0番台からの改造機を含め42機が投入されており、このうち25両が寝台特急牽引用のP形・17両が高速貨物牽引用として開発されたF形とされています。
ブルートレイン牽引機としての印象が強い機関車ですが、1000番台の登場により国鉄時代には既にその任務を解かれ、トップナンバーの501号機のみがJR東日本の継承。その他の機関車はJR貨物に継承されています。
その後はイベント列車での活用だけでなく、隣接するJR貨物高崎機関区へ貸し出されて貨物列車牽引をする機会もありました。
栄光のブルートレインを牽引したEF65形500番台のトップナンバーという多大な功績のある機関車をみすみす手放すことは考えにくく、将来的な鉄道博物館保存などを視野にした自社での活用を前提に考えていることと推測されます。

経歴を考えれば将来的に鉄道博物館収蔵に落ち着きそうな価値のある機関車ですが、EF65形500番台には東芝が保存するP形の535号機、碓氷峠鉄道文化むらにはF形の520号機と両形態が外部に現存します。
JR東日本の保存車への考えとして、同一形式が他所で保存されていることが背景と推測される保管車両の解体が過去にも数多く見られましたので、昨今の苦しい状況下だと悲しい末路も全くないとは言えません。
JR東日本としてはこのほか尾久車両センター(前:田端運転所)にPF形の1102,1103,1115号機の3機が稼働可能な状態となっていますが、2024年3月以降は特に稼働機会が限定的でこちらも心配な状態です。
こちらも先述のEF64 1053号機と同様に保存車的な価値が見出せるかどうかも微妙なところで、良くてスノープロウなしの1115号機に可能性がある程度でしょうか。
DD51形

JR東日本には29両と継承された数こそ多いものの、普通・イベント客車牽引列車の減少で2000年代までに急速に数を減らし、その後しばらくは高崎車両センター高崎支所に4機が残る体制となっていました。
DD51 842号機はお召牽引機、888号機と895号機はお召予備機、897号機のみ通常塗装と東日本エリアの非電化路線でお召列車が運行される際の牽引機を配置している拠点としての使命もありました。
これら4機は高崎支社管内のSL運転に関連した運用以外にも、遠方で実施されるSL列車での伴走、小野上駅からのバラスト(砕石)輸送の工事列車牽引や秩父鉄道のSL入出場といった幅広い用途で使用されてきました。
DD51 842号機を中心にJR東日本管内各地のイベント列車や車両基地公開などのために貸し出される機会も多くなっていました。
このほか、かつてDD51形配置には清水・新清水トンネル区間の停電時に非常用救援機として使用する意図も込められていたようで、2000年代にはこれを見越した単機での上越国境越えの試験も実施されたそうです。

長らく続いた4機体制は近年の機関車牽引列車淘汰の動きとともに崩れ、897号機は2019年5月、888号機は同年10月に廃車を目的とした配給輸送が実施されています。
今回は残されていた842号機・895号機がその使命を終えることとなります。
先述の上越国境救援をどこまで意識しているのかは明らかになっていませんが、GV-E197系の想定する最大構成の3重連での試験や、「自動ブレーキによる被けん引に対応するための可搬式読替装置を搭載可能な構造」とされることが示されたGV-E197系200番台(TS08編成)がSLに被牽引される試験が問題なく完了すれば、いよいよDD51形が残される余地もなくなりそうです。
DD51形の保存機はトップナンバーの1号機が碓氷峠鉄道文化むらと近場にあるのをはじめ全国各地に点在しており、お召列車牽引機の842号機が保存対象になるのか否かが注目ポイントでしょうか。
DD51形はJR貨物が旅客会社より先に淘汰を完了しており、旅客会社ではJR西日本所有機がまだ活躍中です。
こちらもそろそろ後継車両が出てきても不思議ではない経年ですが、EF65形やクモヤ145系とともに事業用として車両牽引を続けています。
今後はJR九州のようにDD200形やDF200形を投入する路線に舵を切るのか、キヤ143形では試験に留まった牽引用気動車を本格的に開発するのか気になるところです。
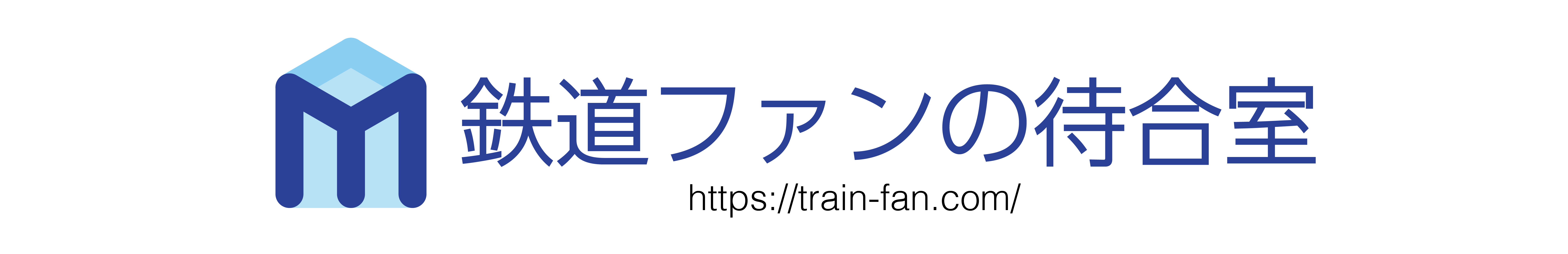












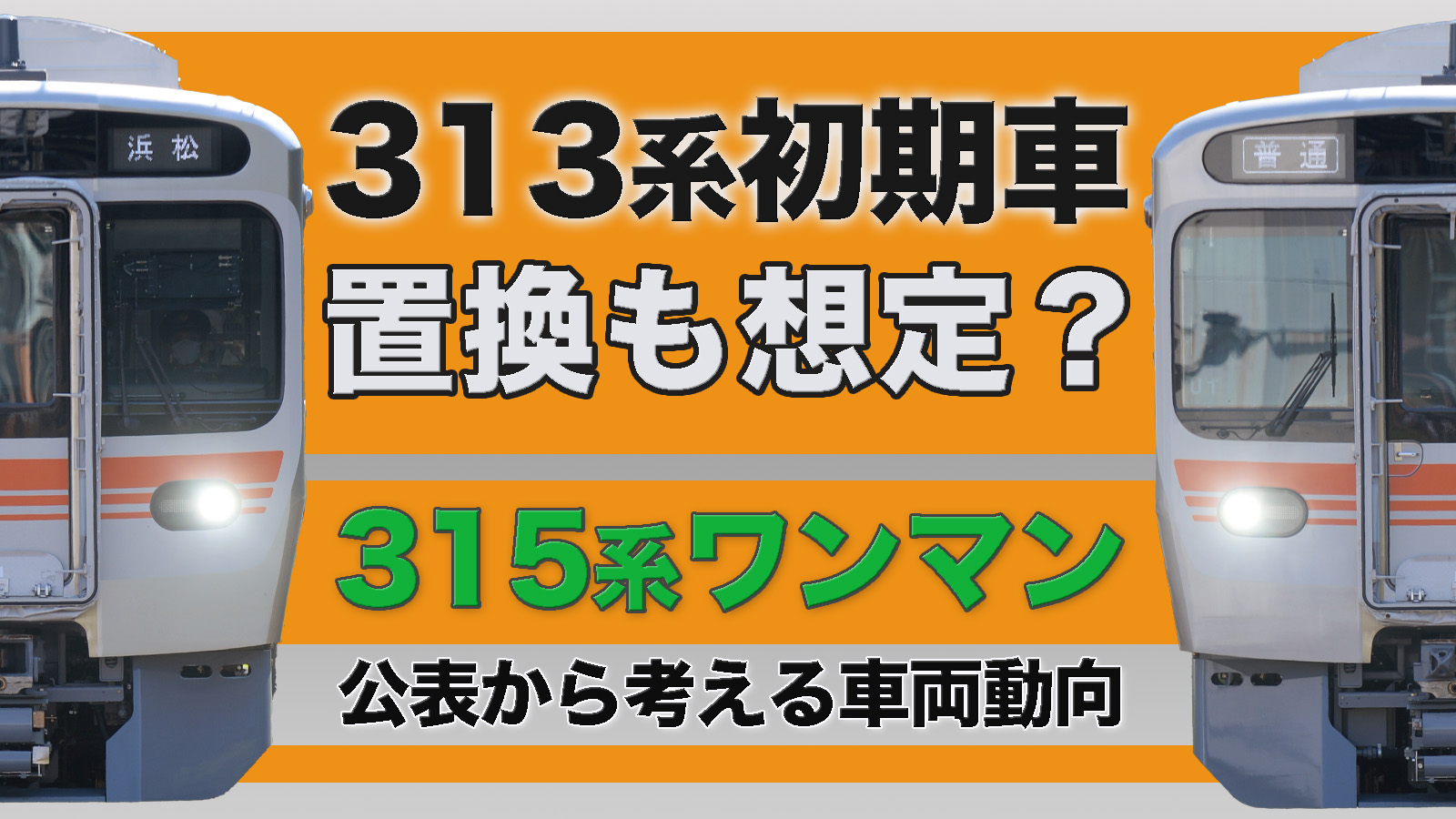
コメント