
JR西日本きのくに線(紀勢本線)・御坊駅(ごぼうえき)構内において、2019年(平成31年)4月14日朝、脱線事故が発生しました。
現場の状況とともに、元乗務員が現場の写真から考察します。
※執筆時点ではJR西日本では事故原因を発表していないため、あくまで推測となります。
関係機関への問い合わせはおやめください。
事故状況は?
概況
2019年(平成31年)4月14日午前6時54分ごろに発生しました。
JR東海・西日本の紀勢本線のうち、JR西日本区間である和歌山市駅〜新宮駅間にはきのくに線という愛称がついています。
このうちの中間駅である御坊駅構内において、入換中の4両編成の電車が脱線する事故が発生しています。
当該車両について
225系5000番台の第11編成が当該編成となっています。
225系5000番台は、関西空港アクセスのために製造された223系0・2500番台の増強と、阪和線系統の老朽化した103系などの既存車両の置き換えを目的に投入された車両です。
この編成に大きな事故歴はありません。
御坊駅について
JR西日本きのくに線の特急くろしお号停車駅でもある大きな駅です。
運行上の折り返し駅として、この駅以北・以南で運行本数が大きく異なります。
駅構内は紀州鉄道の0番線のほか、JRの1〜3番線がありますが、脱線箇所はそれに併設された留置線です。
事故の原因として考えられるものは?(4/15加筆)
状況から見る可動K字クロッシングの動作不良
御坊駅構内の当該箇所は、可動K字クロッシングという特殊分岐器が存在しています。
留置線から本線を跨いで引き上げ線に行くという配線ですが、ここで通常では向かうことができない本線に先頭車が進んでしまったというのが写真等から明らかになっています。
通常のポイントレールのように進路の変更は出来ないものの、本線側の高速通過のために可動部分があります。
このような特殊分岐器の動作不良は通常のポイントレールより頻度が高く、文献によっては8倍の発生頻度という統計もあります。
構内入換時の取扱ミス説
以上の状況から考えられるのは3つで、まずは構内入換運転中の取扱ミスです。
運転士養成時のミス事例としてもよく取り上げられる、入換信号冒進→異線進入→泣き別れ脱線という可能性です。
当該箇所は入換信号機ではなく入換標識であるものの、留置線→引き上げ線で進路が構成出来ていない状況で入換信号機が動作する構造とは考えにくく、この進路構成が完了する前に突っ込んでしまったというパターンです。
時間帯的に運転士は泊まり明けである可能性が高く、ミスが起きやすい時間でもあります。
しかしながら、入換信号冒進の時点で保安装置が作動するほか、ポイントを異線進入してしまった場合は指令所に連絡する必要もあるため、無断で動かしてはいけません。
ポイント不転換説
次に考えられるのは、線路設備側の異常です。
可動K字クロッシングが完全に切り替わっておらず、車輪が通過した反動で転換してしまい、途中から別の進路になってしまったというものです。
(通常は、列車が走行している際には切り替わらないようロックがされます)
しかしながら、構成出来ていないのに完了したとして信号が開いてしまうなら、それも問題です。
信号機・保安装置の不完全説
もし切り替わっていないのに進路が構成できてしまって、入換運転が出来るというシステムであったならば、そもそもの構造欠陥であり、保安上の観点から大きな問題となりそうです。
マスコミからのバッシングは確実?
JR西日本では、福知山線脱線事故発生以来、社内一丸となって安全対策に取り組んでいます。
福知山線脱線事故当時、メディアから散々バッシングされた旧型保安装置も、その後の大規模投資によって改善されています。
先頭車への転落防止幌(関連記事参照)設置など、自社に落ち度が少しでもあれば、どこの会社よりも大規模な投資もしてきました。
しかしながら、新幹線での異音インシデントのように、過剰に叩かれる状況は変わっていません。
今回の事故も、福知山線脱線事故と全く異なる原因であることは間違いないものの、おそらく今後大きな批判の的となってしまうことでしょう。
JR西日本も、当時のように個人に責任を押し付けるのではない、客観的な判断をしてくれることを祈ります。








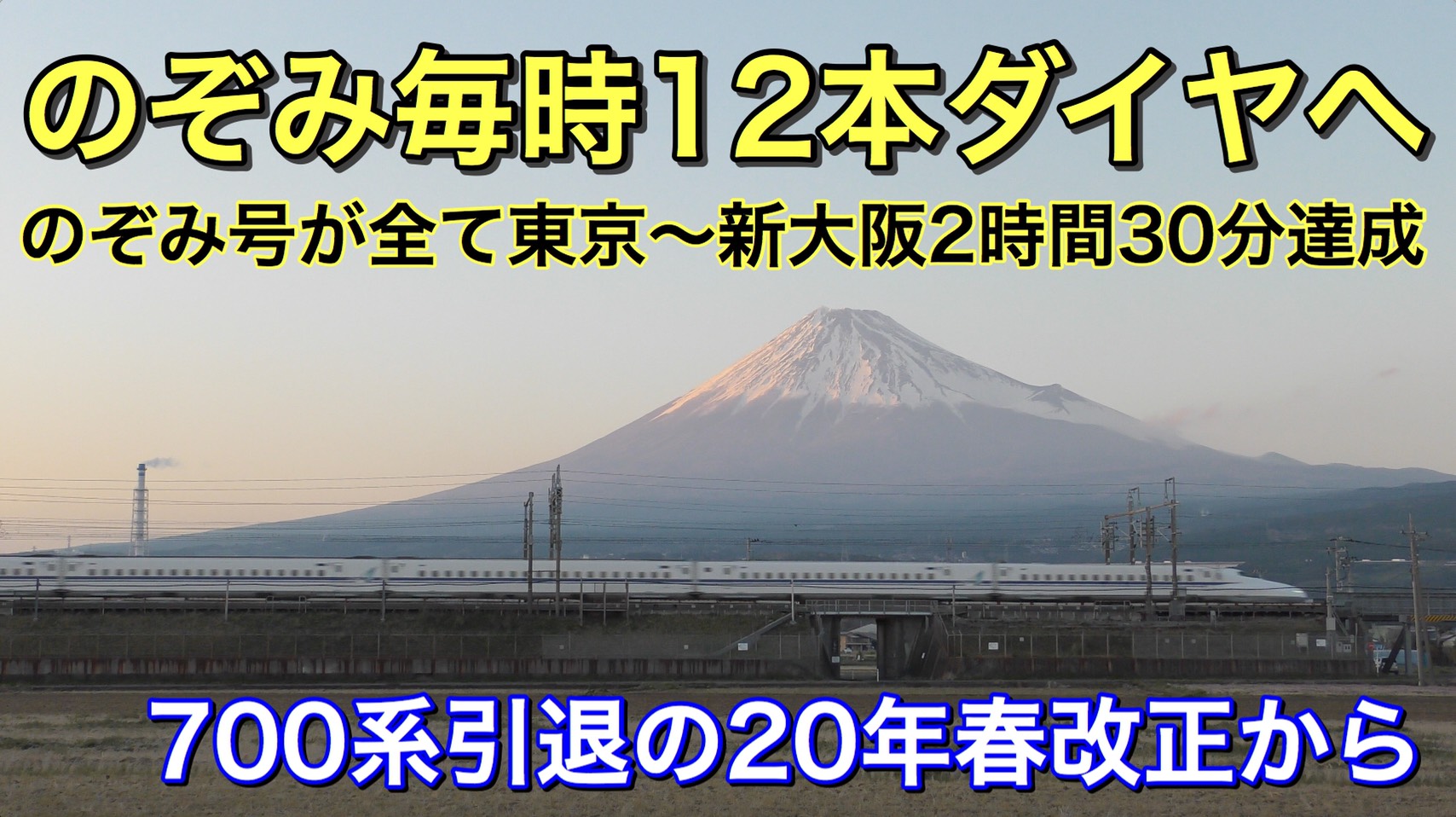
コメント