
1919年の伯備線開業から8月10日でちょうど100年を迎えました。
山陽〜山陰連絡としては唯一となる電化路線・現在も貨物列車運行という点が目立つ伯備線のこれまでとこれからに迫ります。
伯備線の開業と電化の理由
伯備線は倉敷~伯耆大山駅を結ぶ路線で、山陰地区と山陽地区を結ぶ陰陽連絡ルートの幹線です。
全線開通は1928年(昭和3年)ですが、電化については1982年の直流電化と大きく遅れています。
これは、1972年の山陽新幹線の岡山駅開業に伴って、米子や松江、出雲市方面のアクセス特急の需要が出てきたことによるものです。
新幹線開業当初はキハ181系が投入されたものの、一部複線化・線路付け替えなどの工事とともに直流電化が進められ、振り子式電車381系が投入されました。
国鉄末期の苦しい台所事情のなかで線路付け替え・新型特急まで同時に行っていることから、この路線の必要性が急増したことがお分かりいただけるかと思います。
伯備線の歴史を大きく変えたのが、現在の看板特急の車両381系というのも少し意外ですね。
現在も貨物列車が運行

伯備線では国鉄時代より貨物列車が運行されています。
黎明期にはD51形3重連が見られる風光明媚な路線としてSLファンが多く集った路線でした。
国鉄末期からは、長年EF64形1046~1050号機が岡山機関区に配置されて専属的に活用されていましたが、近年の愛知機関区集約の流れで同機関区の一員となったために様々な塗装の機関車を見られるようになりました。
集約前後の過渡期には0番台も乗り入れて大きく話題になりました。
イベント列車も多数運行
陰陽連絡唯一の電化路線ということもあり、イベント列車・団体臨時列車も多数運転されました。
客車ジョイフルトレインが多く存在したJR西日本では、EF64形9号機がJR西日本岡山電車区に継承、伯備線内の客車列車・工臨列車を専属的に担当していました。
同機の引退後は、平坦な新見駅までの間についてはEF65形牽引で行われています。
伯備線が止まらない伯備線の駅!?
伯備線に存在する布原駅は、芸備線からの直通列車・キハ120系のみが停車するという少し変わった運行形態となっています。
この布原駅は国鉄時代に布原信号所だったものを、民営化と同時に駅へ格上げして誕生しました。
新見駅 – 備中神代駅間に乗り入れている芸備線。駅名板などの案内でも芸備線の駅として案内されていますが、書類上はれっきとした伯備線の駅です。
利用者が非常に少ないゆえの措置ですが、伯備線全列車が通過する伯備線の駅という形態は非常に珍しいですね。
並行している本数が少ない路線にのみホームがある例ならば、東海道本線・伊東線の来宮(きのみや)駅や、中央本線・身延線の金手(かねんて)駅など他の地域でも多く存在します。
このほかにも、井原鉄道が清音駅〜総社駅間で乗り入れており、本数が少ないながら複雑な運行がされているのも伯備線の魅力です。
2018年集中豪雨では迂回貨物も登板
2018年に岡山・広島を襲った集中豪雨では、山陽本線にも路盤流出などの甚大な被害をもたらしました。
山陰本線経由での迂回ルートも検討されていた中、伯備線と山陽本線倉敷駅以東を早期復旧することで、伯備線・山陰本線経由での迂回貨物が運行されました。
原色機へのヘッドマーク掲出で地元ファンにとって元気づけられる列車運行にもなりました。
電化・有効長に優れた伯備線ならではのインフラが、関西・九州の物流の架け橋となったことで、中国地方以外からも大きく注目されました。
伯備線のこれから
今後の大きな話題として、特急やくも号用381系・普通列車115系の代替車両の登場が気になりますね。
特に特急車両の置き換えは中長期計画ですでに発表済のほか、伯備線にはJR四国の新型8600系の乗り入れ・試運転実績もありますので、利用者からは引き続き振り子式車両となるのか、車体傾斜装置使用となるのか、はたまた紀勢線くろしお号のように低重心化のみの措置となるのか。
普通列車についても新型227系のバリエーションとなるのか、関西地区223系などの転用となるのか。
どちらも情報は少ないところですが、今後の動き次第で今までの景色は一新されそうですね。
両形式ともに個性的な車両が多いですので、記録は早めに進めたいところです。
関連記事はこちら
サムネイル画像:写真AC
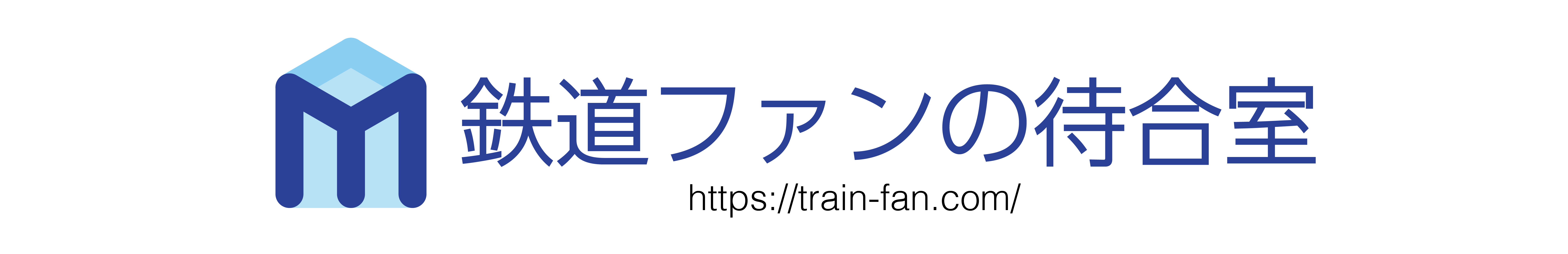








コメント
普通列車の置き換えは、227系の新製投入(2000番台?)だと思います。
223系などは、機器更新などが始まっていたはずなので、転用は、ありえないかと…