
11月30日に控えたJR線・相鉄直通の準備も最終段階となり、常時両社の2~3編成が直通試運転に充てられる大詰めを迎えています。
もはや沿線利用者なら一度は見かけたことがあるという方が多いくらいに日常的に行われている試運転ですが、直通運転開始後に運用されない新宿駅以北でも乗務員訓練が行われています。
そもそも試運転の目的って?
新型車両が運転開始までにたくさんの試運転を行いますが、大きく下記の3種類に分けられることが一般的です。
ざっくりと分類すると下記の通りです。
①誘導障害試験
納車後、最初に深夜に低速で走っている試運転はだいたいこちらです。
列車の床下機器等のノイズが踏切や信号の妨げにならないかを確かめるものですね。
これが上手くいかない例もたまにあり、都営5500形デビュー遅れの原因とも言われています。
②性能確認試験
こちらは各種機器類が求められる性能・設計通りの性能を出すことが出来るかを試すものです。
今回の相鉄の事例では、E233系とほぼ同一ですが、相鉄線内とは異なるJRの環境で求められる性能を出せるかを試すために、東海道線根府川駅まで入線して話題となりました。
③乗務員訓練
車両側の仕様に問題が確認されなければ、最後に乗務員訓練を行います。
担当する全乗務員が運転習熟をするために実施されるため、試運転の中でも比較的見かけることが多く、撮影しやすい被写体となりますね。
現在相鉄直通関連の試運転はすべてこの段階に来ています。
埼京線・川越線で乗務員訓練が続く理由
以上を踏まえると、営業運転では原則入線しないとされている埼京線・川越線については、性能確認試運転だけしておけばいいように感じます。
しかしながら、最近になって埼京線・川越線区間でも各駅に停車する形での試運転が続いています。
埼京線特有の保安装置ATACSの試験のため、最初の川越車両センター入線は東北貨物線経由で行われましたが、それ以降は埼京線経由で行われていますので、保安装置の問題はなさそうです。
これは推測の域を出ないものの、埼京線の乗務員区所の問題がありそうです。
今回、相鉄直通を担当する乗務員さんは沿線に他の区所が存在しないため、湘南新宿ラインとあずさ号を担当している新宿運輸区が担当する模様です。
一方で、埼京線の列車については、大宮運輸区が担当しています。
つまり、埼京線・川越線で乗務員訓練をしているのはダイヤ乱れ時に埼京線の乗務員が乗れるようにするためであり、既存の新宿・品川発の試運転とは別で実施しなければならないという可能性が高いですね。
余談となりますが、担当乗務区の違いがあるため、埼京線の快速停車駅変更・一部区間減便は相鉄直通の為の乗務員確保とは直接的な関係はありません(人事異動でどちらも微調整はあるかと思いますが)。
いずれにせよ、埼京線の高架区間や川越線の単線区間を走るシーンは営業運転開始後はなかなか見られなくなるはずです。
今回はJR東日本と大手私鉄初の直通運転(従来は地下鉄経由の小田急のみ)あって、かなり慎重な試運転頻度となっています。
JR的には旨味が少なそうに感じるこの系統ですが、かなり念入りに試運転をしていますね。
初年度利用動向次第では品川駅方面への運転なども期待できそうです。
関連記事はこちら
動画資料集
YouTubeチャンネル【鉄道ファンの待合室資料館】にてこの列車についての動画を公開しています。チャンネル登録・コメント・評価もお願いします。
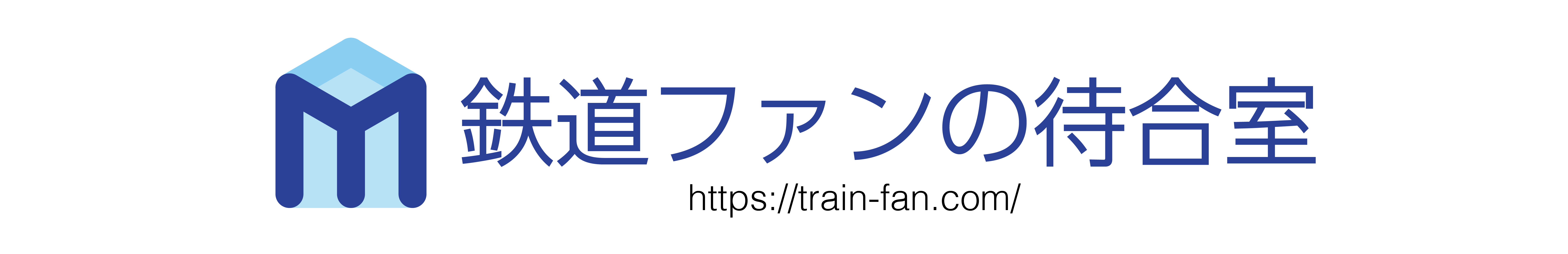









コメント